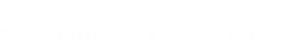【メディアインタビュー】(弁護士ドットコムニュース)「「「災害復興法学」岡本弁護士が語る熊本地震「生活再建」に向けた5つの課題」
2016年5月21日 岡本正のロングインタビュー「「災害復興法学」岡本弁護士が語る熊本地震「生活再建」に向けた5つの課題」がウェブメディア(弁護士ドットコムニュースほか)に掲載されました。>記事全文はこちら
「災害復興法学」岡本弁護士が語る熊本地震「生活再建」に向けた5つの課題
熊本地震から1月あまりが過ぎた。今も現地では多くの人が避難生活を送り、不安な日々を過ごしている。そのような中、熊本地震の義援金の差押さえを禁止する法案が5月19日に衆院を通過するなど、生活再建に向けた制度設計の動きも出始めている。
東日本大震災の生活再建の実態を、被災者4万人の法律相談から分析し、「災害復興法学」を提唱する岡本正弁護士は「義援金の差押さえ禁止法案は、緊急提言が功を奏したが、残された課題はほかにもある」と話している。特に、次の5つのポイントが重要だという。
・「災害関連死」の適切な認定
・「半壊」でも被災者生活再建支援金の対象にすること
・東日本大震災では利用が伸び悩んだ「被災ローン減免制度」の徹底活用
・「被災マンション法」「大規模災害借地借家法」の適用
・「災害時要配慮者」の支援に向けた被災者台帳システムの活用
これらのポイントについて、岡本弁護士が詳細に語った。
●「災害関連死」は適切に認定されるか
建物の倒壊や津波など、地震によって直接亡くなったのではなく、避難生活による体への負担など、震災の影響で死亡することが「災害関連死」です。災害弔慰金の支給対象になりますから、災害関連死にあたるかどうかが適切に認定されているかどうかは非常に重要な問題です。
そのためには、事例の分析が重要になってきます。東日本大震災では、3000件を超える事例が災害関連死かどうか審査されました。しかし、これらの事例がデータベース化されていません。東日本大震災で発見されたであろう教訓も眠ったままになっている状況です。この記録を国などで精査する必要があると思います。
また、心配していることは、死因や死亡時期などによる杓子定規な「統一基準」が作られることです。災害関連死については、ひとつひとつ丁寧に、「この災害がなければ、その方が、その時、その場所で、その病気で亡くなることはなかった」という震災と死亡との相当因果関係を、亡くなった方の直接の死因等だけではなく、属性、環境、避難の態様、病歴、年齢といった情報から、きめ細やかに判断していく必要があります。
そして、その判断は、県に委託するのではなく、市町村がそれぞれ独自に災害弔慰金支給審査会を組織し、行なってほしいと考えています。市町村や地域が異なれば、被災の状況は異なります。事例ごとの特殊性を無視して一律に判断しようとすれば、そこからこぼれ落ちてしまう事例があると考えられます。
基準を必要以上に緩やかにして、災害関連死と認定すべきだと考えているわけではありません。ただ、しっかりとした法律上の評価を加えた上で、正当に相当因果関係を認定すべきです。そうした判断なく、災害関連死と認定されなかった場合、残された遺族は2度にわたって被害を受けることになります。家族が亡くなった瞬間と、災害関連死と認定されなかった瞬間です。東日本大震災で、自治体の災害弔慰金支給審査会の委員を務めた弁護士らも同様に述べています。
災害関連死に認定されても、問題は残っています。災害弔慰金が満額500万円支給される「主生計者」の基準が非常に厳しいという点です。災害弔慰金は、主たる生計者が亡くなった場合500万円支給されますが、この主生計者にあたらない場合、半額の250万円の支給になります。主生計者にあたるかどうかは、残された家族に103万円以上の収入があったかで判断されています。
たとえば、死亡した夫の年収が600万円で、妻が103万円以上の収入を得ていた場合、夫は「主生計者ではない」と認定されてしまうわけです。こうした結論に違和感はないでしょうか。これは厚生労働省の通知に基づくものですので、速やかに改定してほしいと考えています。
●「半壊」にも被災者生活再建支援金の対象拡大を
被災者生活再建支援金は、住宅の被害と再建手法に応じて最大300万円を支給する制度ですが、現状では、「全壊」と「大規模半壊」の罹災証明を受けている方にしか支給されません。熊本の住宅被害で圧倒的に多いと見込まれる「半壊」と「一部損壊」は、現状では支給対象になっていないのです。
しかし、「半壊」と「一部損壊」の住宅に引き続き住むことは困難な場合が少なくないと思います。しかも、半壊では、仮設住宅に入居できない可能性があります。「半壊」「一部損壊」の被災者は、不安を抱えながら住宅に住み続け、自力で再建をしなければならないのです。ちょうど、支援の「はざま」に落ちてしまうわけです。また、盛土など地盤の損壊があっても、家屋の損壊がない場合に、実際は住めない状況でも被害認定が低くなるというミスマッチが起きています。
「半壊」の被災者にも少しでも支援が行き届くよう、支給対象を拡大する法改正を検討して欲しいと思います。一方で、半壊などの場合でも、災害救助法の運用を弾力的にすることで、仮設住宅の入居を認めることは可能です。仮設住宅の入居要件について柔軟な対応をするという総理の発言もあったところですので、現場での運用と住宅の確保が期待されます。
●「被災ローン減免制度」を徹底活用
震災の影響で、既存の住宅ローンと再建のためのローンや生活費を二重に負担したり、既存の債務が支払えなくなってしまう、いわゆる「二重ローン」を解消し、速やかに経済再生を遂げるべく設けられたのが「被災ローン減免制度」です。熊本地震では、2015年12月にできた「自然災害債務整理ガイドライン」の利用を検討することになります。
東日本大震災では、被災ローン減免制度として「個人版私的整理ガイドライン」ができましたが、周知不足と制度ができるまでに震災から4か月経過してしまっていたことから、あまり活用されませんでした。熊本地震では、積極的な周知と活用をしてほしいと思います。金融機関にとっても、早期に顧客が経済再生することは大きなメリットです。東日本大震災では、金融機関からダイレクトメールを発出し、顧客に被災ローン減免制度の説明会開催を周知するなどした例があります。
熊本で活用が期待される「自然災害債務整理ガイドライン」は、最終的には被災者(債務者)が裁判所に「特定調停」という手続きを申し立てる必要があります。高額の費用がかかるわけではないですが、利用への心理的なハードルを少しでも下げるべく、手数料を無償化してほしいと思います。「特定非常災害特別措置法」の項目(第7条)を政令で追加指定することで対応できます。
●熊本地震にも「被災マンション法」「大規模災害借地借家法」の適用を
民法や区分所有法(マンション法)の規定では、所有者全員の同意をとらないと、分譲マンションを解体、更地化といった措置をとることができません。全員の同意が得られず半壊マンションが放置され、余震などでさらにマンションが崩れてしまうような事態を防止する必要があります。
こうしたリスクを避けるために、マンションなどの解体、売却の要件を緩和した「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」は、被災したマンションに限って、5分の4の同意が得られれば、更地にして土地を売却するなどの対応をとることができると定められています。
また、「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(大規模災害借地借家法)」の適用も検討すべきです。たとえば、従前の賃貸人が建物を再築して、改めて賃貸をしようと考えているときには、元の賃借人に「通知」する制度があります。これにより、賃借人が元々住んでいた場所へ戻る機会を与えることができます。現在起きている賃貸借紛争の解決に寄与する可能性もあると考えます。
法務省や国土交通省は、現場の被害を速やかに調査して、熊本地震でもこれらの法律を適用する政令をそれぞれ発出してほしいと思います。
●「災害時要配慮者」の支援に向けた被災者台帳システムの活用に期待
被災者台帳システムというのは、罹災証明書の発行と合わせて被災者の台帳をつくり、現状やニーズを一元的に把握し、紐付けることで、シームレスに被災者を支援することを目的としたものです。熊本県下の市町村で次々と導入され、「罹災証明の発行の迅速化が期待」などと報じられています。その点ももちろんですが、特に、重度の障害者や高齢者など「災害時要配慮者」への支援のために効果的に活用されることを期待しています。
たとえば、重度の障害を負った方や、一人暮らしの高齢者の方が数千人という規模でいる可能性があります。こうした被災者には行政や支援者の側からリーチして、支援の手を差し伸べることが必要になりますが、自治体の担当者だけでは対応することは困難です。他の部署や公的機関、場合によっては民間の支援団体などにも協力してもらう必要が出てきます。
本来は個人情報の取り扱いにはさまざまな制限がありますが、災害対策基本法の改正により、被害者本人の同意がなくても被災者台帳を策定し、自治体間で情報を共有することが可能になっています。一方で、公的機関だけでは対応が難しくなることが予想されるので、情報を信頼できる民間の支援団体にも渡す必要があると思います。そのような場合でも、本人の同意だけが要件ではなく、自治体の個人情報保護審議会による答申や、自治体から支援団体への業務委託などで個人情報を適切に活用することも可能だと思われます。